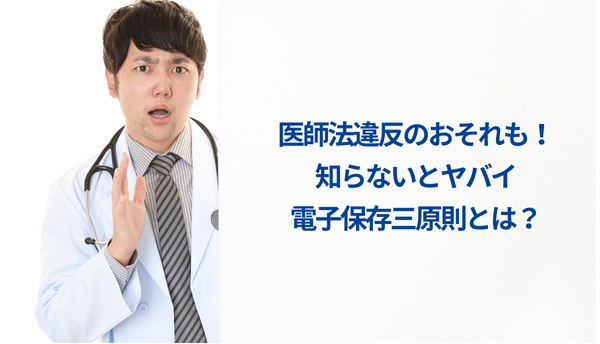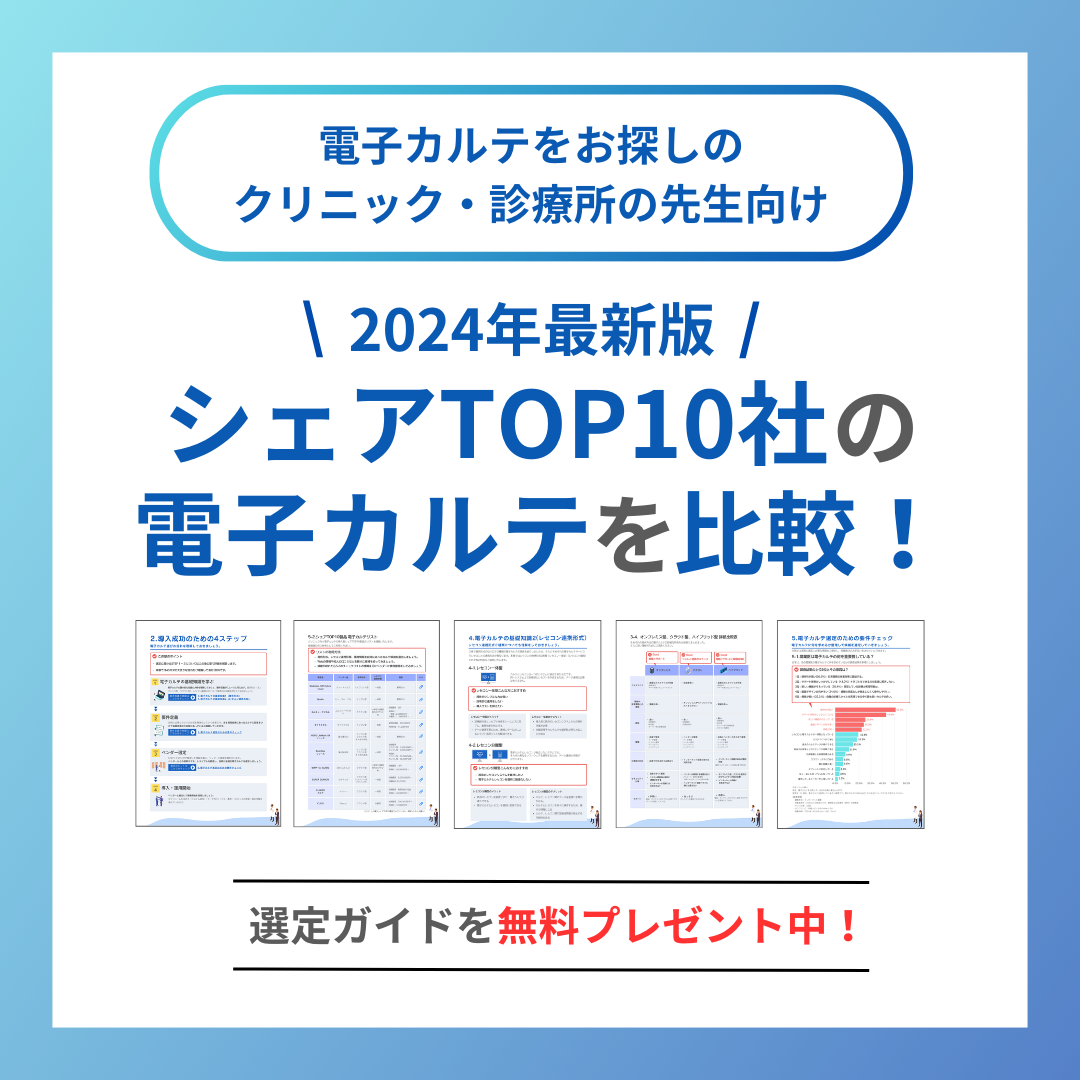電子カルテ
厚生労働省
電子処方箋とは?いつから運用?電子処方箋の仕組みや導入に必要なもの
2024.10.30
患者さんに薬を処方するときに発行される処方箋。2023年からは、従来の紙の処方箋に加え「電子処方箋」の運用が始まっています。
そこでこの記事では、電子処方箋の概要や仕組み、導入に際し準備しておきたいことなどについてご紹介します。処方箋の電子化をスムーズに行いたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

目次
電子処方箋とは
まずは、電子処方箋の概要をご説明しましょう。電子処方箋とは従来のような紙の文書ではなく、デジタルデータで発行する処方箋のことです。
患者の同意があれば、複数の医療機関・薬局をまたいで過去3年間の薬剤情報を医師・薬剤師が閲覧可能となります。医療情報がデータ化されることで、共有を容易にするというわけです。複数の医療機関・薬局で処方箋の情報が連携されることで、過去のお薬情報にもとづいたスムーズでスピーディな医療を受けられます。
電子処方箋はいつから?義務化するの?
電子処方箋は、2023年1月から運用が開始されています。ただし現状のところ電子処方箋そのものの義務化はされていません。
電子処方箋自体は義務化されていませんが、電子処方箋の運用にあたって必要なオンライン資格確認は2023年4月から義務化されているため、注意が必要です。
現在では紙の処方箋を使っても従来通りの運用が可能となっていますが、今後はさらに多くの医療機関で処方箋の電子化が進んでいくと見られます。
電子処方箋の仕組み
それでは、電子処方箋はどのような仕組みで取り扱われるのかについても見ていきましょう。
電子処方箋は、国(厚生労働省)が運営している「電子処方箋管理サービス」を通して、医師・薬剤師が必要に応じ処方箋情報をやり取りできる仕組みによって運用されます。
基本的には医師がシステムに処方箋情報を追加し、薬剤師がそれを見て薬を処方するという運用方法になっています。
電子処方箋を利用したときの処方から調剤までの流れ

さて、電子処方箋を利用した場合に、処方箋の発行から調剤までの流れはどのようになっているのでしょうか。ここでは、電子処方箋利用時の処方箋発行→処方受付→記録までの一連の流れを詳細にご紹介します。
1.処方箋の発行
病院やクリニックにて、医師が電子データの形で処方箋を発行します。この際、医師は電子処方箋管理サービスを確認し、現在の患者の容体と過去に処方された薬の情報をもとに、今回の処方内容を決定することになります。
2.薬局にて処方受付
薬局では、マイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証と引き換え番号により、電子処方箋管理サービスから対象となる処方箋を確認します。
処方箋の内容が確認できたら、調剤を開始します。なお、このときに電子処方箋管理サービスを利用して、過去の処方・調剤情報を照会します。その上で重複投薬がないことや、併用禁忌に抵触していないかなどを確認します。ちなみに、疑義照会に関しても電子処方箋管理サービスに登録され、それらの情報も医師と連携されます。
3.調剤記録や保管
発行された処方箋のデータは電子的に保存できます。調剤済みの電子処方箋は、電子署名入りの状態で原本保管する取り扱いとなります。また、調剤結果等の医師等への情報提供が、いつでも電子的に可能となっています。
電子処方箋のメリット・デメリット
処方箋が紙の文書から電子データに変わることで、メリットやデメリットはあるのでしょうか。ここでは、電子処方箋を取り扱うことで生じるメリットやデメリットについてご紹介します。
電子処方箋のメリットとは
・医療サービスの向上
電子処方箋が導入されることで、複数の医療機関や薬局で患者さんの薬に関する情報が連携されます。もし患者さんが複数の医療機関を受診したとしても、各医療機関の薬剤情報をすぐに確認できます。
薬局では、手入力で薬剤情報を登録する必要がなくなり、業務リソースを患者対応に集中させられます。患者とのコミュニケーションを適切に図れることで、服薬指導も確実に行えるでしょう。
また、飲み合わせの良くない薬の組み合わせを確認できるため、効能の重複を避けることが可能です。また、医療機関の間で情報共有ができると、疾患やアレルギー、副作用などに関してもすぐに知ることができます。
・医療機関の円滑な連携が可能
紙文書の処方箋では、その都度患者さんとやり取りをしなければ調剤を始めることができませんでした。しかし電子処方箋を導入すれば、受付から診察~処方まで、オンライン上で完結できます。従来は患者さんが薬局を訪問してから必ず待ち時間が発生していましたが、電子処方箋では事前に調剤することも可能なため、待ち時間を短縮できます。
・処方箋作成にかかるコスト削減
処方箋を紙で作成すると、紙にかかる費用や記入・出力の手間が必ずかかってきましたが、電子処方箋ならそれらのコストを削減できます。
このほか、膨大な分量の紙の処方箋を保管する場所が不要になるメリットもあります。また、処方箋偽造の防止につながったり、本人確認が容易になったりする点もメリットといえるでしょう。
電子処方箋のデメリット
数多くのメリットがある電子処方箋ですが、少ないながらにデメリットも存在します。まず挙げられるのは、新しい電子処方箋のシステムを運用するにあたり、関わるすべてのスタッフが使い慣れるまでに時間がかかってしまう点でしょう。
また、電子処方箋を取り扱うシステムの構築にも、一定の時間がかかります。しかし、運用開始後の業務効率の向上を考えると、さほど大きなデメリットにはなってこないとも考えられるでしょう。
電子処方箋の発行を始めるのに必要なもの

電子処方箋の運用を始めたいと思った場合、どんな準備をしておけば良いのでしょうか。ここでは、電子処方箋発行を開始する際に準備すべきもの・ことについてご紹介します。
オンライン資格確認の導入
オンライン資格確認とはマイナンバーカードを専用の機械で読み取り、クラウド上のシステムによって患者さんの保険に関する情報を確認する方法です。従来は保険証の提示による窓口担当者の内容確認を経て患者さんの情報を都度入力していました。このシステム登録に多くの時間がかかってしまっていましたが、オンライン資格確認の導入によって、マイナンバーカード1枚で保険情報を確認できます。このように受付が短時間で済むようになり、業務の効率化を図れます。
HPKIカードの発行申請
電子処方箋には、電子署名の記載が必要になります。HPKIカードとは、厚生労働省が認可している電子署名で、電子処方箋でもこの署名を用います。医師や看護師、薬剤師の国家資格が電子的に証明することが可能となります。
なおHPKIカードは日本医師会電子認証センターや医療情報システム開発センター、日本薬剤師会認証局で発行してもらえます。
電子処方箋に対応したソフトやシステムの導入
電子処方箋を管理するためのソフトやシステムも必要です。多くのソフトやシステムがあるため、自院に合うものを選定しましょう。
電子処方箋利用申請を行う
準備ができたら、電子処方箋利用申請を行います。申請の詳細に関しては、以下のリンクをご覧くださいませ。
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-25.html
電子処方箋を導入するならEMシステムズへ
EMシステムズでは、「電子処方箋スターターキット」をご用意しています。ここでは、EMシステムズの電子処方箋を始めるにあたってお得に開始できるスターターキットの特徴や特色をご紹介します。
スターターキットの特徴
スターターキットは「電子処方箋対応プログラム」、「ICカードリーダー1台」、「電子署名ライブラリー」の計3点がセットになったもの。キットの申し込みは、HPKIカードの申請・発行のタイミングを合わせて行いましょう。あらかじめHPKIカードを申請しておき、申請の完了登録が終わってからスターターキットを申し込むことがおすすめです。その後電子処方箋の利用登録を行い、開始日入力→運用スタートとなる前に設定作業を行いましょう。運用開始できたら必要書類を発行し、補助金の申請をします。
スターターキットの導入メリット
スターターキットを導入することで、電子処方箋を導入するために必要な対応プログラムとICカードリーダー、電子署名ライブラリーの3点を1度に揃えられ、運用開始までがスムーズになります。
電子処方箋スターターキットは、EMオンラインSHOPにて注文可能です。なおご注文の対象となるのは、オンライン資格確認を導入されている医療機関様に限られますのでご了承ください。
まとめ
この記事では、電子処方箋の概要や導入のメリット、スムーズな導入に便利なスターターキットをご紹介しました。これからできるだけ早期に電子処方箋を導入したいとお考えであれば、EMシステムズまでお問い合わせください。
この記事を書いたライター

氏名 株式会社EMシステムズ
1980年創業の医療(クリニック・保険薬局)、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を行う企業です。現在は北海道から沖縄まで、多くの全国の医療・介護施設様に当社の各種システムをご利用いただいております。
ピックアップ記事

電子カルテの種類(クラウド型・オンプレミス型)と選び方のポイント

電子カルテメーカーを比較検討する際に重視したい選定要件

電子カルテの導入費用は?費用相場やコストを抑える方法について