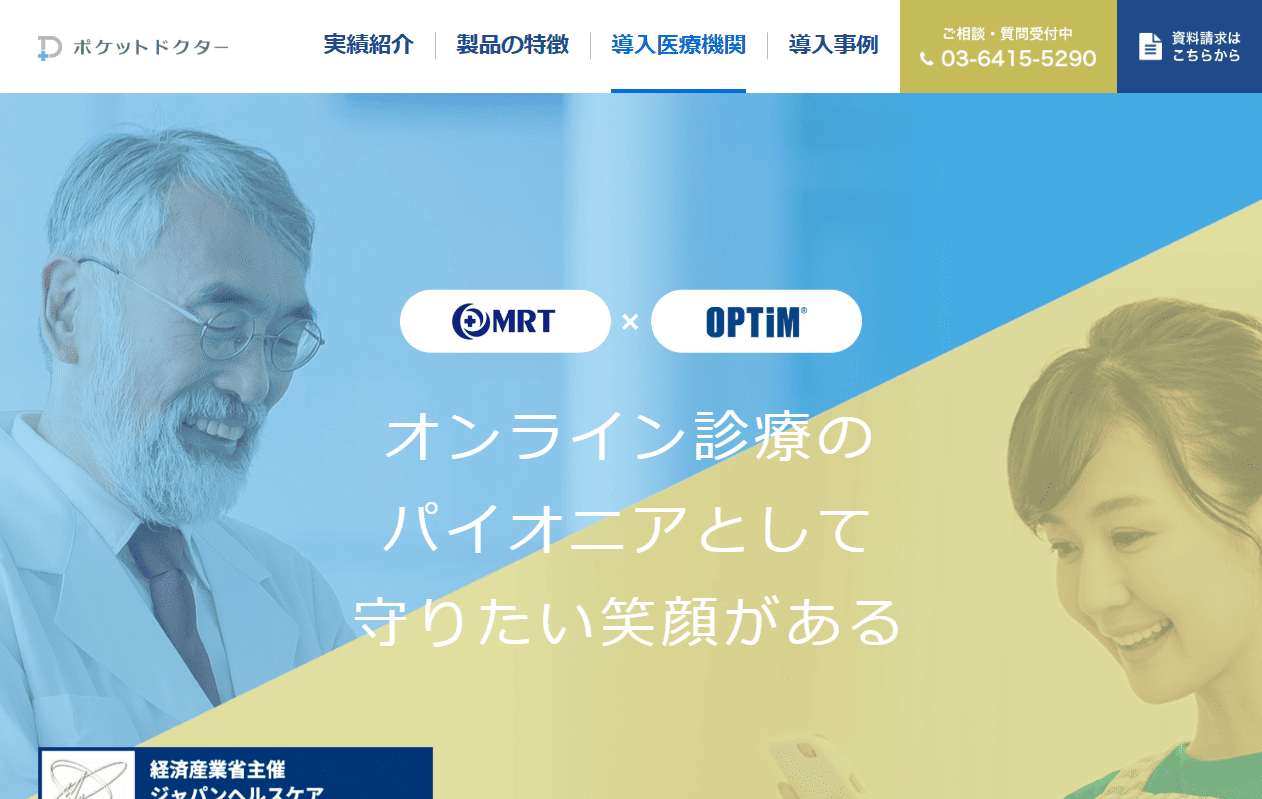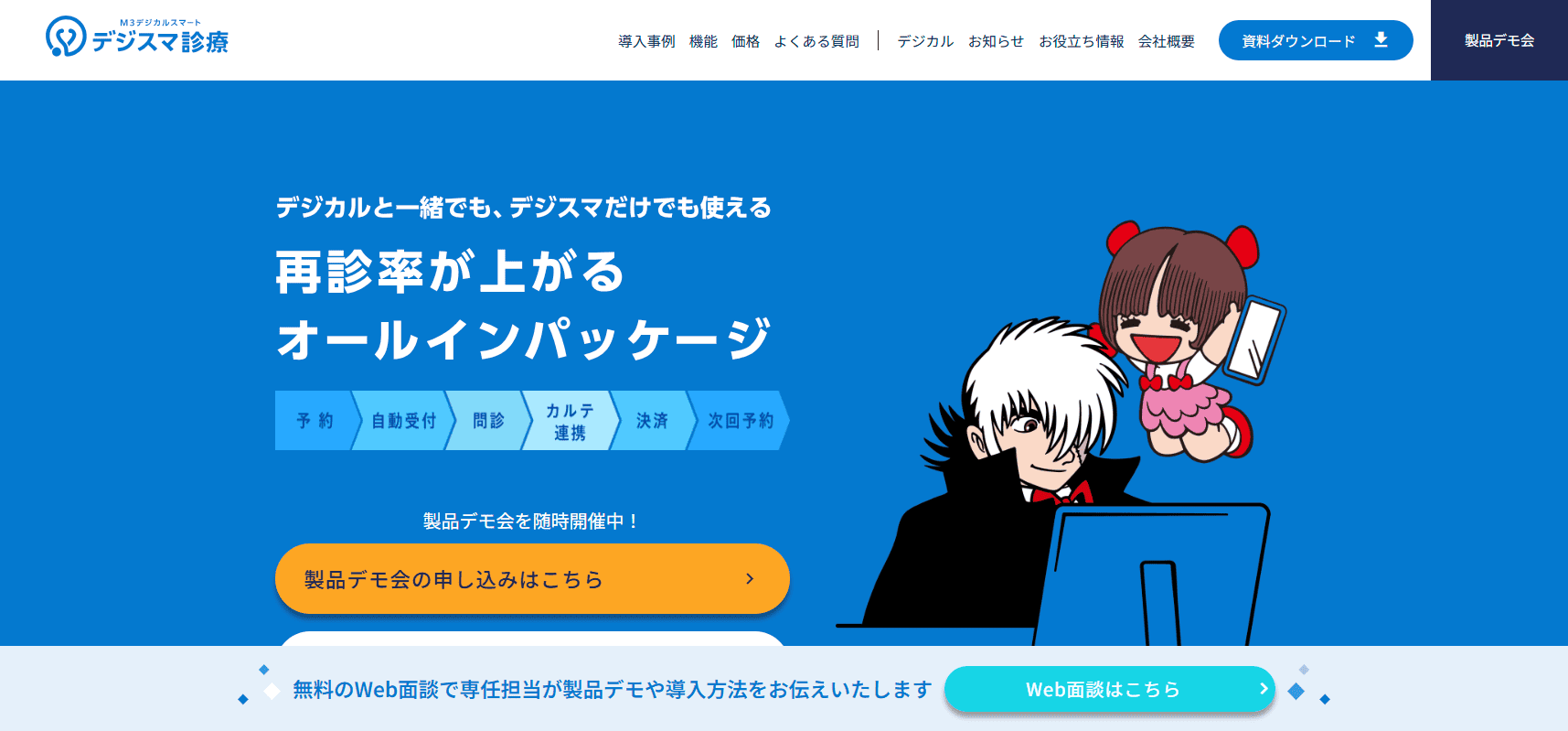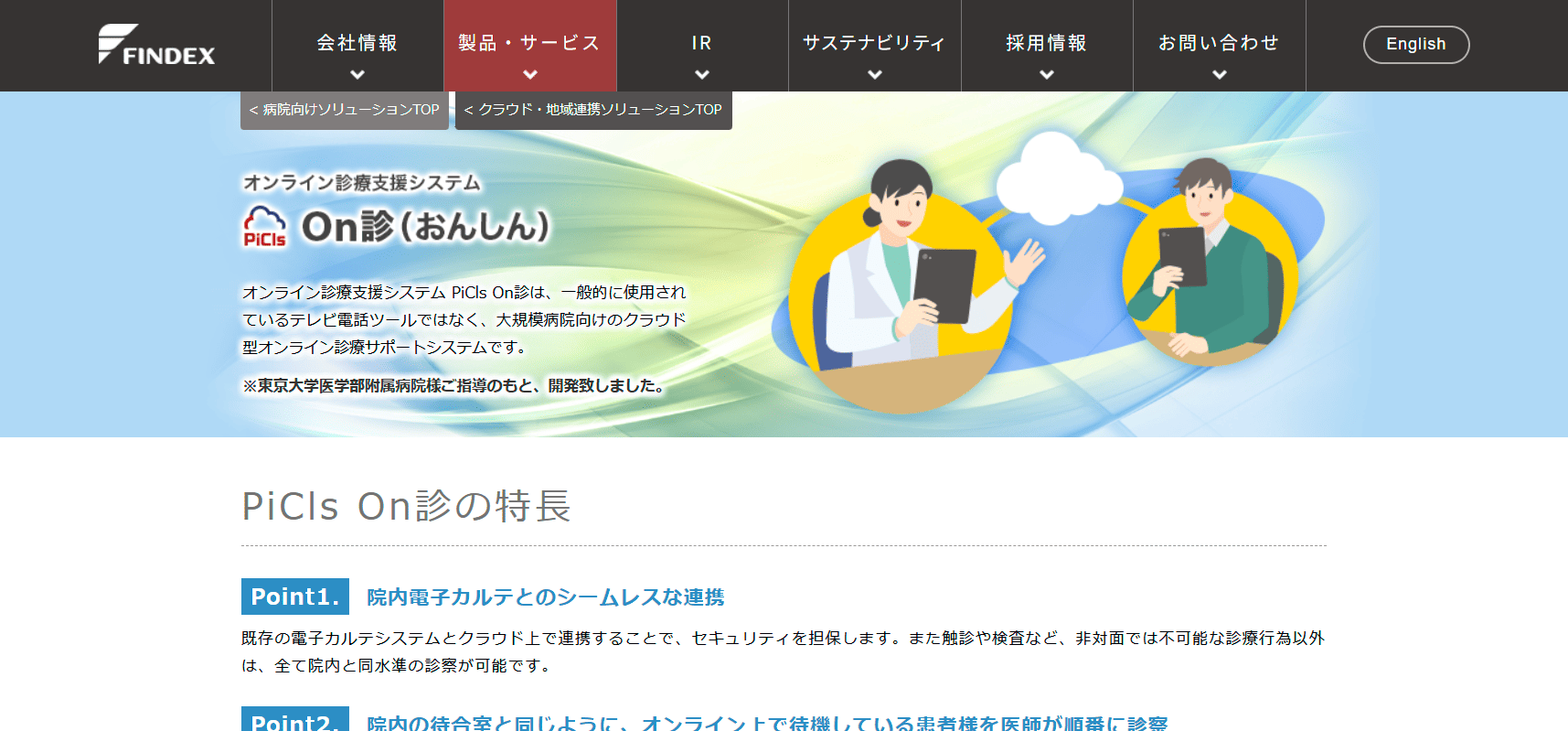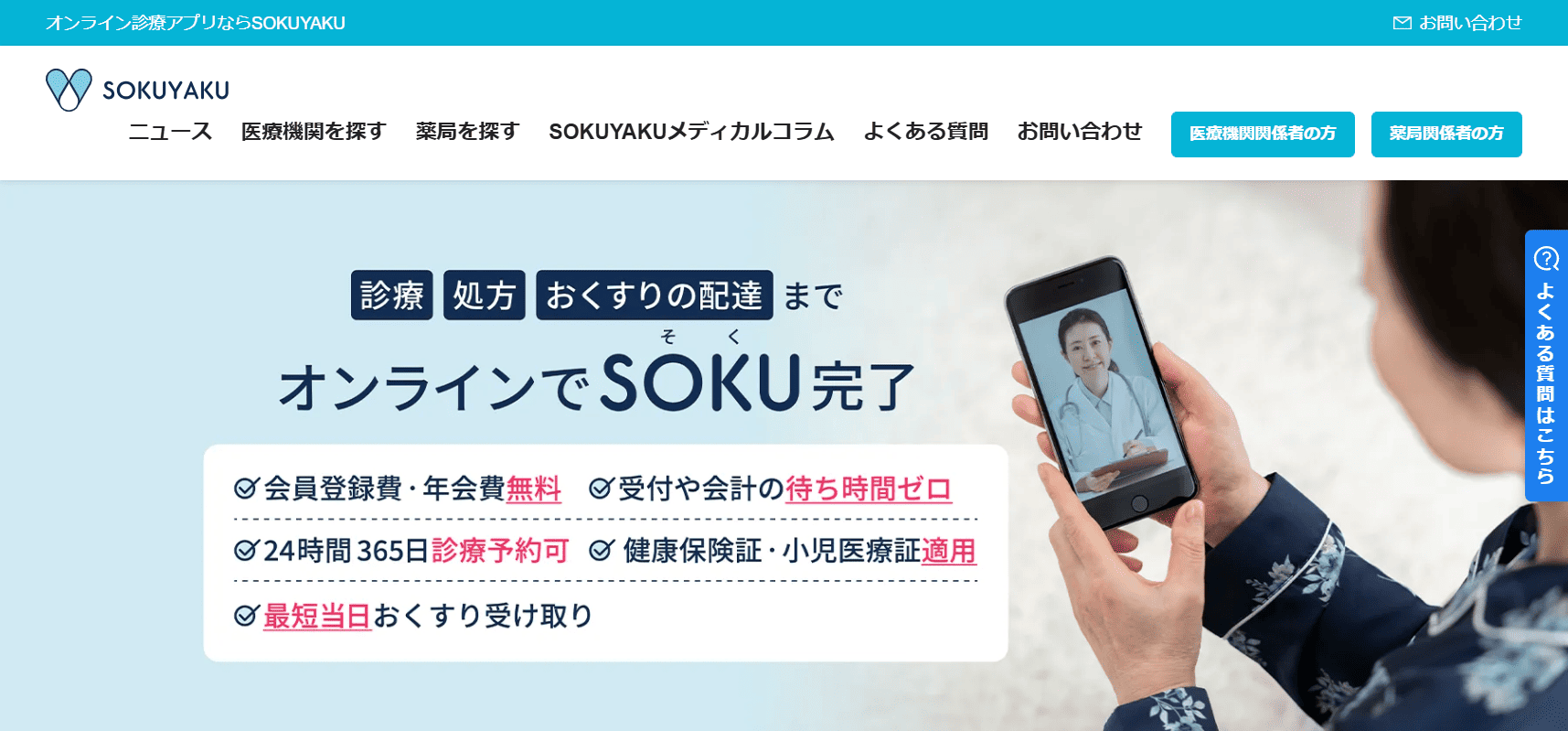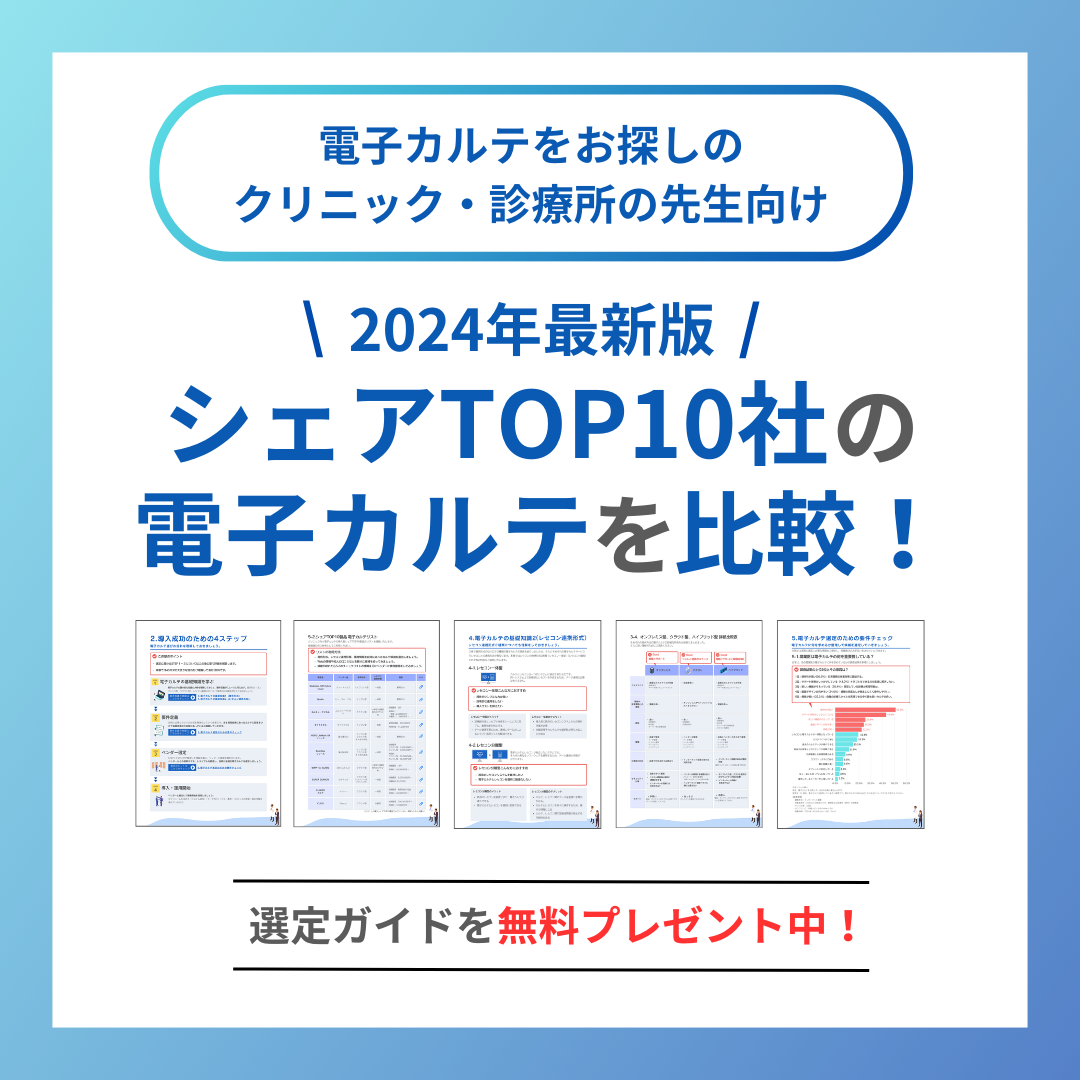集患
オンライン診療システムの選び方|必須機能とおすすめサービス9社を解説
2025.01.16
医療現場で注目を集めているオンライン診療システム。通院が難しい患者の利便性向上だけでなく、医療機関の業務効率化にも寄与しています。本記事では、オンライン診療を支える基本機能や導入のメリット、システム選定時のポイントについて分かりやすく解説します。さらに、実際に導入する際の注意点や運用を成功させるコツもご紹介します。オンライン診療の導入を検討中の方はぜひご覧ください。

目次
オンライン診療システムの基本機能と特徴
オンライン診療システムとは何か?その役割と期待される効果
オンライン診療システムとは、医療従事者と患者がインターネットを通じて診察を行うための仕組みを指します。特に、遠隔地や通院が難しい患者にとって重要な医療手段となっています。このシステムは、医療の質を保ちながら、患者の利便性を向上させるだけでなく、医療現場の業務効率化にも寄与します。診療予約や問診、処方箋の発行など、従来対面で行っていた医療行為をオンラインで実現することで、医療従事者の負担軽減も図れます。
※オンライン診療システムの導入についてはこちら
必須機能一覧|オンライン診療を支える基本的な機能
高品質なビデオ通話・チャット機能
患者と医師が顔を合わせて診察を進めるビデオ通話機能は、オンライン診療における基本です。これに加え、テキストベースのチャット機能は、簡単な質問や診療メモの共有に役立ちます。これらの機能は、診察の精度を高め、患者との信頼関係を築く重要な役割を担います。
電子カルテ・予約管理システムとのリアルタイム連携
電子カルテシステムとの統合により、患者の診療履歴を簡単に参照できるようになります。また、診療予約管理システムと連携することで、予約枠の可視化や効率的なスケジュール管理が可能です。これにより、患者の待ち時間を減らし、医療機関の業務効率が図れます。
処方箋発行機能と医薬品配送サポート
診療後に必要な処方箋を自動的に発行し、薬局への連携や患者宅への医薬品配送もサポートします。この機能は特に忙しい患者や高齢者にとって利便性が高く、オンライン診療の価値をさらに高めます。
付加価値を高めるサポート機能|選定時に見逃せないポイント
支払い・保険請求機能の統合で事務作業を効率化
オンラインで診療を完結させるためには、支払い手続きや保険請求がシームレスに行える仕組みが必要です。これにより、患者の手間を省き、医療機関の事務作業負担を軽減します。
データ分析・レポート機能で診療効率を改善
患者データの蓄積と分析を行い、診療パフォーマンスの向上や患者満足度の向上に役立てる機能も注目されています。特に、診療データを可視化してトレンドを把握するレポート機能は、戦略的な運用の鍵となります。
オンライン診療システムを選ぶ際に重視すべき5つのポイント
自院の診療科目や規模に応じたシステムを選ぶ
自院の診療科目や規模に合ったシステムを選ぶことが、成功の鍵です。例えば、慢性疾患管理に特化したクリニックでは、患者の継続的な健康管理をサポートする機能が重要です。一方、小規模クリニックでは、コストパフォーマンスの良いシンプルなシステムが適しています。
操作性と直感的なUIとなっているか
オンライン診療システムは、医師や看護師、事務スタッフが日々使用するツールです。複雑な操作が必要なシステムでは、スタッフの負担が増えるため、操作性の良い直感的なUIを持つシステムを選びましょう。
セキュリティ対策と法規制遵守がされているか
オンライン診療では、個人情報の漏洩を防ぐためのセキュリティ対策が重要です。特に、データ暗号化やアクセス制限、GDPRや日本の個人情報保護法への準拠など、法規制に適合したシステムを選定することが必要です。
導入費用と運用コスト
初期導入費用や月額費用が高額すぎると、運用に負担がかかります。また、システム更新や追加機能の費用についても確認し、長期的な視点でコストを評価することが大切です。
サポート体制|導入後も安心して運用できるサポートが必須
導入後に問題が発生した場合、迅速に対応してもらえるサポート体制が整っているか確認しましょう。特に、システム障害時の対応やトラブルシューティングに強いサポートが求められます。
比較するべき主要なオンライン診療システム9選
1.MAPs サキドリ
特徴
MAPs サキドリは、オンライン診療を効率化するためのクラウド型診療支援システムです。診療予約や、来院前の問診やオンライン決済にも対応し、診療業務を一元管理できる点が特徴です。また、患者満足度・再診率を高める機能として、スムーズな受診フローとシンプルな操作性を重視しており、医療従事者だけでなく患者にも利用しやすい設計となっています。電子カルテ「MAPs for CLINIC」に標準搭載されており、追加費用なしで利用できる利便性も魅力です。
対応規模
主に無床の中小規模クリニックを対象としており、コスト効率を重視したい医療施設に適しています。特に地域医療の効率化を目指すクリニックにとって、診療効率の向上と患者アクセスの改善に役立つツールです。
公式ページ:https://service.emsystems.co.jp/maps_series/for_clinic/sakidori01/
2.CLINICS(クリニクス)
特徴
CLINICS(クリニクス)は、オンライン診療に特化したクラウド型システムで、予約管理、ビデオ通話、オンライン決済を一体化したプラットフォームです。直感的に操作できるユーザーインターフェースが特徴で、医師と患者の双方にとって使いやすい設計となっています。また、電子カルテとのスムーズな連携が可能で、診療業務の効率化を図ります。診療予約から診察、決済までを一貫して管理できるため、医療機関の運営負担を軽減し、患者満足度の向上をサポートします。
対応規模
CLINICSは、中小規模クリニックを主な対象としていますが、幅広い診療科目に対応可能です。特に多忙な診療現場での効率化を求める医療機関に適しており、幅広い患者層へのオンライン診療提供を可能にします。
公式ページ:https://clinics-cloud.com/online
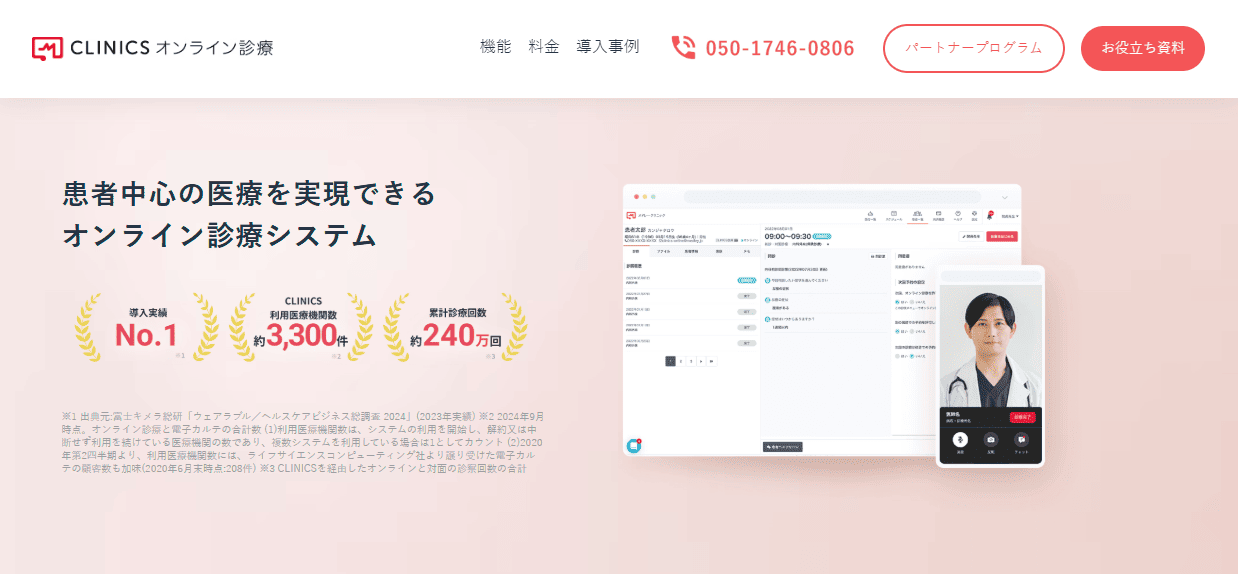
3.YaDoc(ヤドック)
特徴
YaDoc(ヤドック)は、慢性疾患患者を対象としたオンライン診療および健康管理アプリと連携したサービスです。患者の状態を継続的にフォローアップする仕組みが整っており、血圧や体重などのデータをアプリで記録・共有することで、医師が患者の生活習慣改善をサポートします。特に、患者自身が健康管理に積極的に関与できるよう設計されており、医師と患者の協力による効果的な治療が可能です。また、服薬指導機能を備え、適切な薬の使用を促進します。
対応規模
YaDocは、慢性疾患診療を主に行う医療機関を対象としています。糖尿病や高血圧症などの慢性疾患管理に特化しており、患者数の多いクリニックや中小規模の医療施設での利用に最適です。患者との情報共有を通じて、診療の効率化と治療効果の向上を実現します。
公式ページ:https://www.yadoc.jp/

4.ポケットドクター
特徴
ポケットドクターは、スマートフォンを活用してオンライン診療を提供するプラットフォームです。患者はアプリを通じて簡単に診療予約ができ、医師とビデオ通話で相談・診察を行うことができます。診療終了後は電子処方箋を通じて薬を受け取れる仕組みが整っており、医療へのアクセスを効率化します。さらに、直感的で使いやすいインターフェースが特徴で、医師と患者双方にとって負担の少ないシステムとなっています。
対応規模
個人開業医や中小規模クリニックを主な対象としています。特に、初めてオンライン診療を導入する医療機関に適したツールであり、地域密着型の医療施設において高い導入効果が期待できます。また、簡単な操作性が幅広い年代の患者にも対応可能です。
公式ページ:https://www.pocketdoctor.jp/med/
5.デジスマ診療
特徴
デジスマ診療は、オンライン診療を効率的に支援するクラウド型システムで、予約、問診、自動受付、決済までを一括で行えるクラウド型診療支援システムです。システムの導入により、医療現場の運用効率を向上させるだけでなく、患者の診療体験を快適にします。電子カルテとの連携が可能で、診療フローの統一化と記録の一元管理を実現します。また、初期設定や操作がシンプルで、デジタルに不慣れなスタッフでも簡単に利用できる点が特徴です。
対応規模
中小規模のクリニックを中心に設計されており、特にオンライン診療の導入を検討している医療施設に適しています。また、コストパフォーマンスが高く、低コストでオンライン診療を導入したい医療機関にも最適です。地域医療や在宅医療を強化する際のツールとしても活用されています。
公式ページ:https://digikar.m3.com/digisma
6.Curon(クロン)
特徴
Curon(クロン)は、オンライン診療に特化したスマートフォンアプリを中心としたプラットフォームです。患者はアプリを通じて医師とビデオ通話で診療を行い、診療後には電子処方箋の発行や薬の受け取りもスムーズに行える仕組みを提供します。医師にとっては、操作が簡単で診療の負担を軽減するシステム設計となっており、電子カルテや決済機能との連携も可能です。さらに、患者とのコミュニケーションを円滑にするための機能が充実しています。
対応規模
Curonは、個人開業医や中小規模のクリニックに最適化されており、幅広い診療科目で活用されています。また、患者層の年齢やニーズにかかわらず柔軟に対応できるため、オンライン診療の導入を検討している医療機関にとって導入しやすいツールです。
公式ページ:https://curon.co/

7.On診(おんしん)
特徴
On診は、医療機関向けのオンライン診療システムで、ビデオ通話による診療、予約管理、電子カルテとの連携機能を一体化したプラットフォームです。診療内容や患者情報を安全に管理するため、高いセキュリティ基準を満たした設計がされています。また、既存の電子カルテや医療システムとのスムーズな統合が可能で、医療現場の業務効率を大幅に向上させることができます。直感的で使いやすい操作画面も特徴で、医療従事者の負担軽減に寄与します。
対応規模
On診は、大規模な医療機関から中小規模のクリニックまで幅広い医療施設に対応しています。特に、診療科を問わず利用可能な柔軟性があり、患者数が多い施設や地域医療に力を入れている医療機関に適しています。また、複数拠点を持つ医療機関でも統一的な運用が可能です。
公式ページ:https://findex.co.jp/products/medical/picls/onshin/index.html
8.CARADAオンライン診療
特徴
CARADAオンライン診療は、患者と医療機関をスムーズにつなぐためのオンライン診療プラットフォームです。このツールは、診療予約、ビデオ通話、電子カルテとの連携、オンライン決済など、オンライン診療に必要な機能を網羅しています。また、患者が使いやすいインターフェースと直感的な操作性を重視しており、デジタルに慣れていないユーザーでも簡単に利用できる設計です。特に、医療現場での運用負荷を軽減する効率的な仕組みが特徴です。
対応規模
CARADAオンライン診療は、小規模クリニックから中規模医療施設まで幅広く対応可能です。診療科を問わず、多様な患者ニーズに応える汎用性が高いツールとして評価されています。また、地域医療や在宅医療に特化した導入事例も多く、患者のアクセス向上をサポートします。
公式ページ:https://lp.telemedicine.carada.jp/
9.SOKUYAKU(ソクヤク)
特徴
SOKUYAKUは、オンライン診療から薬の受け取りまでを一貫してサポートするサービスです。患者はスマートフォンを通じて医師の診察を受け、処方箋をオンラインで発行してもらえます。その後、指定の薬局で薬を受け取ることが可能で、忙しい方や通院が難しい方にとって便利なシステムです。また、初期費用やシステム利用料が無料で、保険外診療の場合のみ手数料が発生するため、コスト面でも利用しやすい点が特徴です。
対応規模
SOKUYAKUは、個人開業医から中小規模のクリニックまで幅広く対応しています。特に、オンライン診療の導入を検討している医療機関にとって、初期費用がかからない点や、シンプルな操作性が魅力となっています。また、患者にとっても使いやすいインターフェースが提供されており、幅広い年齢層に対応可能です。
公式ページ: https://sokuyaku.jp/
オンライン診療システム導入のメリット
業務の効率化
オンライン診療システムは、予約から診療、決済に至るまでの一連の流れを自動化します。これにより、スタッフが単純作業に費やす時間を削減し、より専門的な業務に集中できる環境を作ります。
患者満足度向上
患者は通院の手間を省き、必要な医療サービスを自宅から受けられるため、満足度が大幅に向上します。特に、慢性疾患や遠隔地の患者にとって、このシステムは不可欠です。
オンライン診療システム導入時の注意点
セキュリティと法規制対応
個人情報保護(GDPRや日本の個人情報保護法)
オンライン診療システムの導入には、個人情報を適切に保護するための法規制に準拠した対策が必要です。GDPRや日本の個人情報保護法に基づき、データの収集や使用の直前に清明な同意を得ることが重要です。
遠隔診療における規制への適応
オンライン診療では導入可能な診療や処方可能な医薬品が制限されています。
厚生労働省のガイドラインを常に確認し、情報を最新にしておくことが重要です。
トラブルを防ぐための運用上の工夫
医師・スタッフの教育・研修
オンライン診療システムを正確に運用し、トラブルを防ぐためには、医師やスタッフへの教育や研修が必要です。例えば、システムの機能の使い方や個人情報の適切な収集と保護に関する知識は、すべての関係者が漏れなく訓練しておく必要があります。これにより、システムトラブルや不正利用の危険性を大幅に削減できます。
システム障害時の対御策
使用するシステムに障害が発生した場合に、迅速な復旧ができる体制を予め構築することも必要です。導入前にシステムベンダーにサポート体制について十分確認をしておきましょう。また、事故発生時の対応プロセスを詳しく作成しておくことで、予期せぬ障害が発生した場合にも即座に対御することが出来ます。
導入後の運用を成功させるためのポイント
運用を円滑化するためのコツ
患者への利用説明の充実
患者がオンライン診療システムをストレスなく利用するために、既存の患者に定期的に説明会などを行いましょう。特にお年寄りなど慣れていない方に対しては、説明の場を設けることで安心感を与えることが出来ます。
システムの定期メンテナンス
頻繁な法改正への対応やセキュリティ対策など、定期的なステムのメンテナンスが必要です。トラブルが起きてからの対応ももちろんですが、トラブルが起きないためのメンテナンス、サポート体制が重要です。
電子カルテや他システムとの連携強化
オンライン診療を最大限活用できる環境を実現するには、電子カルテや決済システムなど他のシステムとの連携が必要です。あとから必要な機能が使用できないという事態にならないよう、自分のクリニックの規模や適性に応じて、必要な機能を備えたシステムを導入することが重要です。
まとめ
自院に最適なオンライン診療システムを選定することで、業務効率化と患者満足度の向上が実現します。導入後は、継続的な運用改善や患者への説明を行い、システムの効果を最大化しましょう。
この記事を書いたライター

氏名 株式会社EMシステムズ
1980年創業の医療(クリニック・保険薬局)、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を行う企業です。現在は北海道から沖縄まで、多くの全国の医療・介護施設様に当社の各種システムをご利用いただいております。
ピックアップ記事

電子カルテの種類(クラウド型・オンプレミス型)と選び方のポイント

電子カルテメーカーを比較検討する際に重視したい選定要件

電子カルテの導入費用は?費用相場やコストを抑える方法について