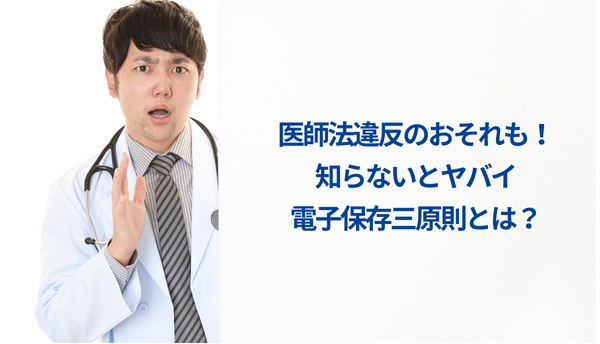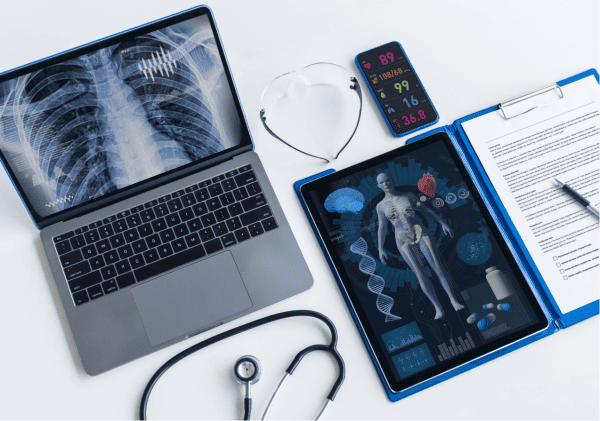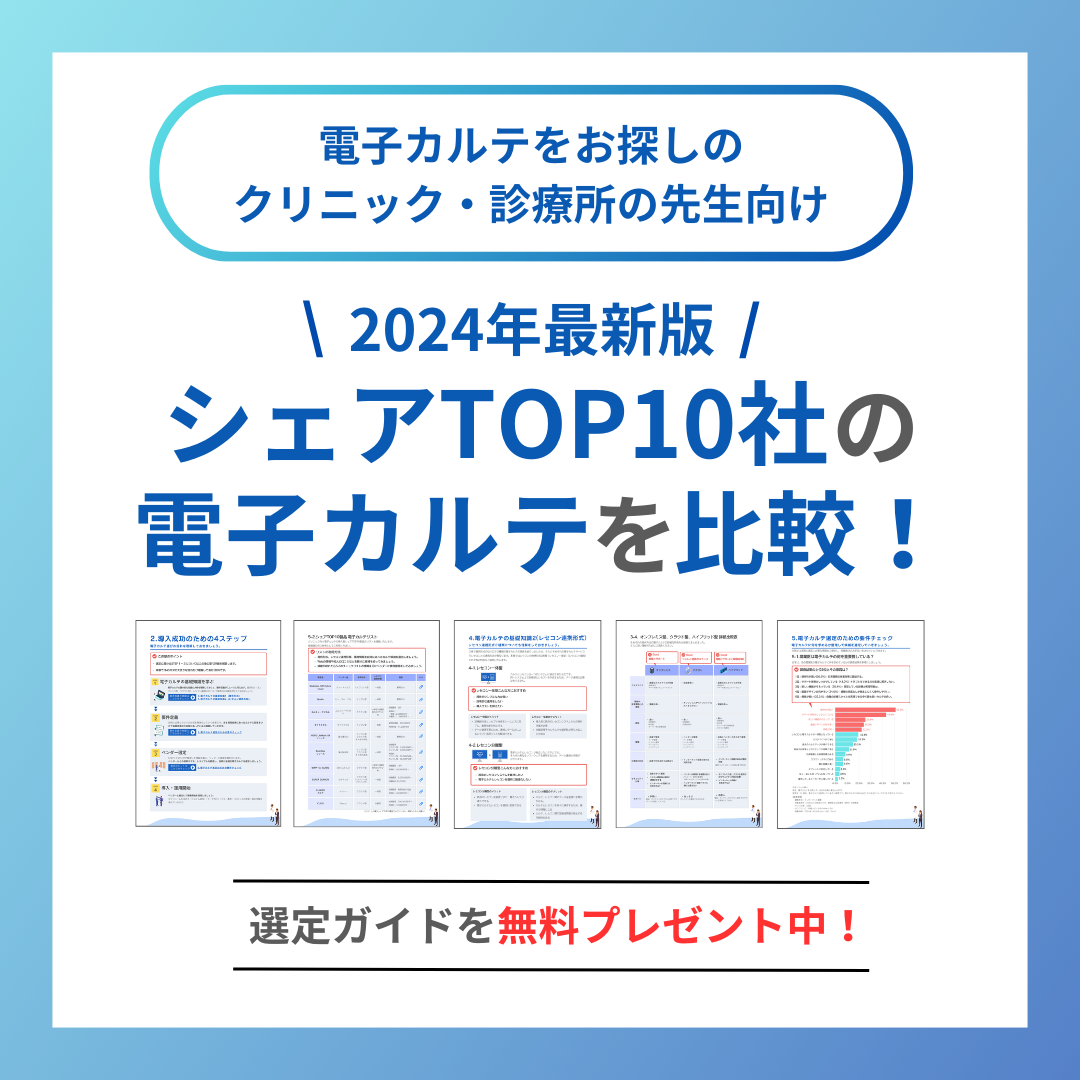電子カルテ
電子カルテの保存期間は?電子カルテと紙カルテの保存期間
2024.10.30
電子カルテシステムを導入し、紙カルテから電子カルテへの移行を図るにあたって、さまざまな疑問をお持ちの方は多いでしょう。そのなかでも、電子化されたカルテの保存期間について詳細を知りたいというニーズは特に多いのではないでしょうか。
そこで今回は、電子カルテの保存期間について解説したいと思います。電子カルテの新規導入をこれからお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

目次
電子カルテの保存期間は?

まずは、法令で定められている電子カルテの保存期間について、紙カルテとの相違点があるのかどうかなどの気になる点をご説明します。
電子カルテの保存期間は5年
電子カルテの保存期間は、「5年間」です。お気づきの方も多いと思いますが、これは紙カルテの保存期間とまったく同じです。保存期間に関して言えば、電子カルテと紙カルテの違いは特にありません。
保存期間の基準
保存期間は分かったものの、「保存期間の開始はいつから?」という疑問をお持ちなのではないでしょうか。法令上の保存期間の基準は診療を開始した日ではなく、診療が「完結(終了)した日」から5年間となっていますので注意しましょう。
20年間は保存しておいたほうが良い?
保存期間は診療終了後5年とされていますが、医療業界では「カルテは20年保存したほうが良い」と言われることが一般的です。もちろん、この「20年保存」は義務ではありません。しかし、医療事故などにおいて損害賠償請求が発生するなどの可能性も考えて、向こう20年間は保存することが望ましいでしょう。
日本医師会は永久保存を推奨
電子カルテシステムを活用しデータが電子化されれば、カルテをさらに長く保存することも可能になります。なお、日本医師会ではカルテの電子化により永久に保存することを推奨しています。これからは、電子化されたカルテを永久保存前提で取り扱うことが求められるでしょう。
電子カルテの導入に際して知っておくべき「電子保存の三原則」
電子カルテを導入するにあたって、知っておきたいことの1つとして「電子保存の三原則」が挙げられます。
「電子保存の三原則」とは、内容改変や削除が容易にできてしまう電子データにおいて、重要な書類をどのように取り扱うべきかを3つの原則として定めたものです。具体的には、真正性・見読性・保存性の3つの基準を満たしていなければならないとされています。
以下に、この3原則について詳細に解説します。
真正性
正当な権限で作成された記録に対し、虚偽の入力や内容の書換え、消去及び混同が防止されていなければなりません。かつ、第三者から見て作成の責任の所在が明確でなければならないとされます。
電子カルテにおいては、カルテデータの虚偽入力や書換え、消去、混同を防止するために、故意または過失、使用する機器・ソフトウェアなどそれぞれの原因に対して、運用も含めて厳重に対応する必要があるでしょう。
見読性
電子媒体に保存された内容を、「診療」、「患者への説明」、「監査」、「訴訟」等の要求に応じて見読可能な状態にしておかなければなりません。また、それぞれの目的に対し支障のない応答時間やスループット(処理能力)、操作方法で読むことができる必要があります。
なお平常時だけではなく、システム障害や災害に備えて見読性を確保する対策も考慮しておくことが必要です。保存データについては定期的なバックアップを実施し、万一の際もデータ消失といった事態を回避できる状態にしておかなければなりません。
保存性
記録された情報が、法令などで定められた期間にわたって真正性を保っている必要があります。またそれにあたっても、見読可能にできる状態で保存されていることが求められます。
(参照:https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/000936160.pdf )
電子化した後の紙カルテの廃棄

電子カルテ導入にともなって、今ある紙カルテを電子化する必要が出てきます。しかし、電子化後の紙カルテについてはどのような処遇が求められるのでしょうか。
基本的には、電子化した後の紙カルテは廃棄して良いこととなっています。ただし、多くの重要な情報が記載されているカルテだけに、通常の廃棄物と同様に捨ててしまう訳にはいきません。
個人情報が記載されているため廃棄にも万全の注意が必要
カルテには患者さんの氏名や住所などの個人情報が多く含まれています。また、患者さんの医療に関する記述そのものも重要な個人情報にあたります。
このため、紙カルテを電子データ化後に廃棄する際も、一般ごみとして処理することはできません。情報漏えいを避けるため、万全の注意を払って廃棄する必要があるでしょう。復元不可能な状態で捨てるためには、溶解処理など特殊な廃棄方法が求められます。
紙カルテを廃棄する際には、機密文書の破棄を専門に行っているプロの業者などへ依頼することが望ましいでしょう。
閉院した後のカルテの保存
カルテ保存において注意したいケースとして、「カルテを管理していた病院が閉院した場合」を想定しておくことも必要です。ここでは、医療機関が閉院した場合にその後のカルテをどう保存するかについてご説明します。
別の病院に事業を承継する場合
カルテに関する責任事項は、医療機関の管理者が負うものとなっています。このため、事業を他の医療機関に継承した場合、基本的にはカルテも継承後の医療機関が引き続き取り扱います。カルテが継承されると、引き継ぎ先にあたる医療機関の管理者がカルテの管理責任も引き継ぐことになります。
医療機関の継承にともなうカルテの移行は、個人情報保護法の例外となっています。事業継承の場合は、顧客の同意なしに個人情報を引き継ぐことが可能になるのですが、このとき注意したい点があります。それは、カルテに記載された個人情報について元の利用範囲を超えて利用する必要がある場合です。そのケースでは、顧客の同意が必要となってきます。
継承を受けたカルテを運用する場合は、取り扱う情報の範囲に十分気を配る必要があるでしょう。
別の病院に承継をしない場合
カルテを他の医療機関に継承することなく閉院した場合は、その医療機関の管理者に5年間(レントゲンフィルムは3年間)カルテを保管しておく義務が課せられます。閉院後も保管義務が生じますので、向こう5年間は場所などを確保の上保管しておかなければなりません。
管理者が死亡した場合
管理者死亡によって医療機関が閉院した場合、その遺族にカルテの保管義務が発生するかと言うと、そうではありません。遺族にカルテの保管義務はありませんが、厚生労働省が提示する「適当な保管場所」は、保健所などの公的機関となっています。
しかし、遺族によって保健所などでの保管が図られているケースは少ないようです。実際には、遺族によってカルテが廃棄されていることもあると見られます。とはいえ、カルテの廃棄には十分慎重になる必要があるでしょう。なぜなら、医療事故による損害賠償義務は遺族に相続されてしまうためです。もし過去の医療ミスや事故などで損害賠償請求が発生した場合、医療行為の正当性を証明するためにカルテが役立つ可能性があるでしょう。
このため、管理者の死亡によって医療機関が閉院した場合にも、遺族の方は一定期間カルテを保管しておくことが望ましいと言えます。
電子カルテの導入ならクラウド型電子カルテシステム「MAPs for CLINIC」
これから電子カルテを導入するにあたって、どのようなシステムを選べば良いか選定に迷っている方も多いでしょう。ここでは、おすすめしたいEMシステムズの電子カルテシステム「MAPs for CLINIC」をご紹介します。
クラウド型電子カルテシステム「MAPs for CLINIC」
EMシステムズの「MAPs for CLINIC」は、直感的な操作で使いやすさを追求した電子カルテシステムです。優れたUIによって良好な操作感を実現するとともに、クラウドシステムによる安定した稼働率を両立。初期ライセンス費用0円の、高いコストパフォーマンスも魅力です。
求めるスペックを満たしたハードウェアをお持ちなら、新規で機器を購入しなくてもお手持ちのPCなどで運用開始が可能。リーズナブルでストレス・フリーな電子カルテシステムです。
「MAPs for CLINIC」は、資料のダウンロードや無料体験も可能。ご興味をお持ちの方は、ぜひEMシステムズまでお問い合わせください。
まとめ
この記事では、法令上の電子カルテの保存期間や紙カルテ電子化後の処遇、電子保存の三原則などについてご紹介しました。電子カルテの導入にともなって紙カルテを廃棄する場合は、確実に廃棄を行えるよう専門業者への依頼を検討しましょう。
また電子カルテの導入に際してシステムの選定にお悩みであれば、今回おすすめした「MAPs for CLINIC」をぜひご検討ください。EMシステムズまでお気軽にご相談ください。
この記事を書いたライター

氏名 株式会社EMシステムズ
1980年創業の医療(クリニック・保険薬局)、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を行う企業です。現在は北海道から沖縄まで、多くの全国の医療・介護施設様に当社の各種システムをご利用いただいております。
ピックアップ記事

電子カルテの種類(クラウド型・オンプレミス型)と選び方のポイント

電子カルテメーカーを比較検討する際に重視したい選定要件

電子カルテの導入費用は?費用相場やコストを抑える方法について