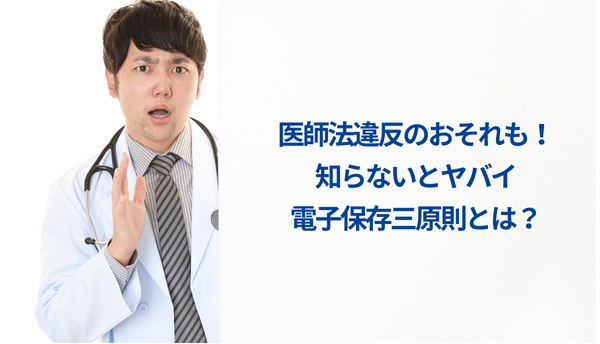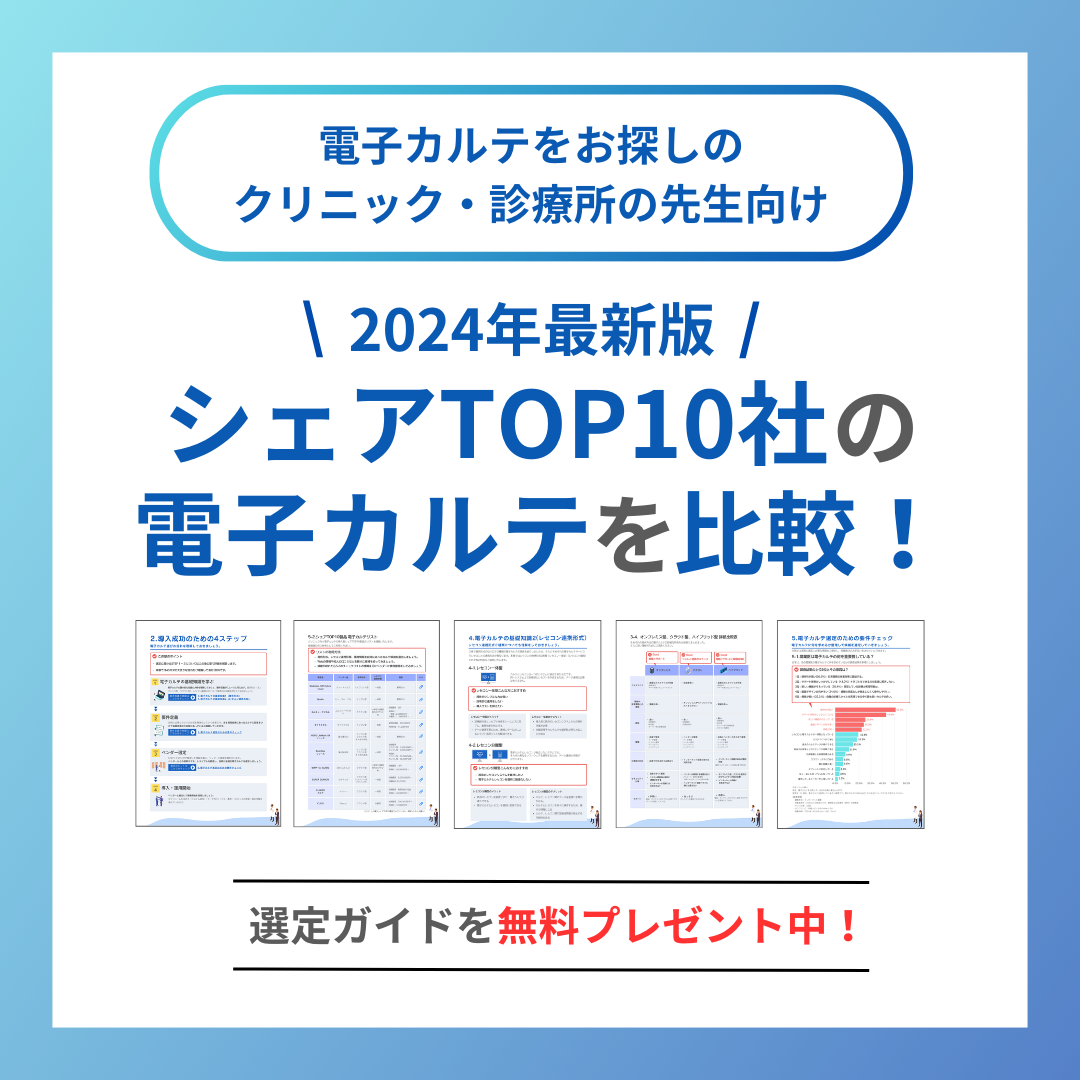電子カルテ
厚生労働省
【2024年最新】政府が推進する「電子カルテの標準化」「標準型電子カルテ」とは?
2024.11.29
政府は、医療機関のDX化を積極的に推進しています。2023年には「経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太の方針2023)※1」が閣議決定され、医療分野におけるデジタル化が重要な施策として位置づけられました。その施策の一つとして、「電子カルテの標準化」「標準型電子カルテの開発」が進められています。遅くとも2030年までに概ねすべての医療機関で標準化された電子カルテの導入を目指すとされており、2024年度から順次、全国の医療機関で電子カルテ情報を共有可能とする仕組みが構築される予定です。本記事では、「電子カルテの標準化」「標準型電子カルテ」とは何か、その現在の状況と今後の展望について詳しく解説します。
※1 参考:厚生労働省内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2023」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001114701.pdf
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2023/2023_basicpolicies_ja.pdf
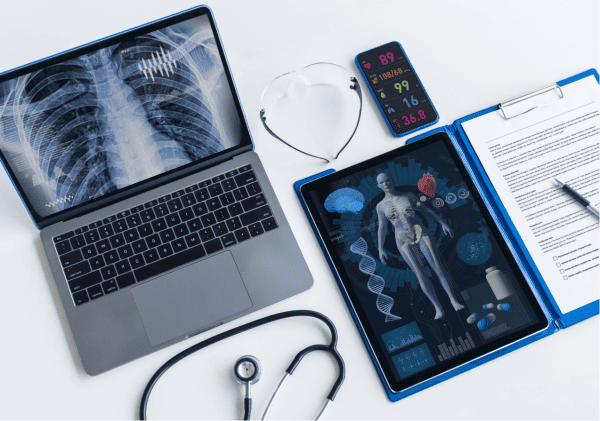
1.医療情報共有の現状と課題
従来の電子カルテは、医療機関ごとに異なるシステムが導入されており、患者の医療情報の共有を円滑に行うことができませんでした。このため、患者が複数の医療機関を受診する際、過去の診療情報が参照できず、重複した検査や治療が行われるリスクがありました。また、災害時などにおいては、患者の医療情報の把握が遅れ、適切な医療提供の妨げとなることも懸念されていました。
2.「電子カルテの標準化」とは?
2-1.「電子カルテの標準化」の定義
電子カルテの標準化とは、医療機関ごとに異なる電子カルテシステムのデータ形式や内容を統一し、医療機関間での情報交換を円滑にするための取り組みです。
2-2.標準化により共有できるようになる情報
「3文書6情報」※2の共有を進めて、順次対象となる情報の範囲を拡大していく予定です。
- ・3文書
診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書 - ・6情報
傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)、処方情報
※2参考:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001309907.pdf
2-3.「電子カルテの標準化」に向けた取り組み
では、具体的にどのような取り組みがなされているのでしょうか。現在進められている取り組みの代表的な内容をご紹介します。
- ・HL7 FHIR(エイチ・エル・7 ファイア)の採用
HL7 FHIRは電子カルテ上で扱われるデータ形式で、医療データを迅速で効率的に統合・交換をするための国際的な標準規格です。これにより異なる医療システム間でも患者データのやりとりが可能になります。
- ・全国医療情報プラットフォームの構築
全国医療情報プラットフォームは、標準化された電子カルテデータを連携するための基盤となるシステムです。このプラットフォームを通じて、全国の医療機関で患者情報を安全かつ迅速に共有できるようになることを目指しています。
- ・医療従事者への教育・啓蒙
標準化された電子カルテシステムを効果的に活用するため、利用者である医療従事者の理解を得ることが必要です。新しいシステムへの導入に抵抗感を持つ医療従事者もいるため、その理解を深め、スムーズな移行を支援できるよう教育・啓蒙活動が行われています。
- ・標準型電子カルテの開発・普及
2020年現在の電子カルテの普及率を見ると400床以上の大規模病院では91.2%と高いのに対し、200床未満の中小規模の医療機関では48.9%、一般診療所では49.9%と高いとは言えない状況です。※3 紙カルテに慣れた医師にとっては、操作を覚える必要があり、金銭面でもコストのかかる電子カルテの導入を不要と考えるケースもあり、このままでは全国での医療情報の共有が達成できません。そこで、政府が主導して、電子カルテの導入に踏み切れない中小の医療機関に向けて標準化の要件を満たした電子カルテの開発を推進しています。詳細は次の章「標準型電子カルテ」とは?で解説いたします。※3 出展:出典:電子カルテシステム等の普及状況の推移(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938782.pdf)
2-4.「電子カルテの標準化」で医療はどう変わるか?
電子カルテの標準化で情報共有が円滑に行われることにより患者、医療機関の双方だけでなく、社会全体としてメリットを享受できると言われています。ではどのように医療は変わるのでしょうか?
患者のメリット
- ・より安全で質の高い医療が受けられるようになる。
過去の診療履歴やアレルギー情報など、重要な情報が医療機関間で共有されることで、誤診の可能性が減ります。また、患者情報が総合的に判断できる材料が医師に提供されるため受けられる治療の質も向上が見込めます。
- ・受診がスムーズになる。
複数の医療機関を受診する場合でも、過去の診療情報は引き継がれるので、待ち時間や説明の時間が短縮されます。
- ・窓口負担額が削減される。
重複する処方や検査の削減や、薬剤の誤処方防止などにより、窓口の負担を下げることができます。
- ・災害などの緊急時にも適切な医療が受けられる。
災害時や旅行先等かかりつけの医師以外から治療を受ける際にも、情報が共有されているため適切な医療を受けることができます。
医療機関へのメリット
- ・業務効率化が上がる。
フォーマットが標準化されることで、情報を入力が簡素化し事務作業が効率化します。
医療従事者はより多くの時間を患者さんへの診療に充てることができます。
社会全体へのメリット
- ・医療データの活用の可能性
標準化された医療情報をAIやビッグデータなどで活用しやすくなるため、医療政策の立案や、新たな医療技術の研究・開発が推進される可能性があります。
- ・医療費の抑制
医療情報の共有による重複検査の削減や、効率的な医療資源の配分により、医療費の抑制に貢献できます。
2-5.「電子カルテの標準化」の課題
メリットが大きい一方で、実現に向けて以下のような課題があるのも事実です。
◆電子カルテのコスト、運用に抵抗感がある医師もいる。
紙カルテの運用に慣れている医師やスタッフにとっては、電子カルテの導入・運用コストや、操作を覚える手間に煩わしさを感じている方が多いのも確かです。※4
解決策として、後述の導入コストが抑えられると言われている「標準型電子カルテの導入」や、「各種補助金の利用を周知する」ことでコストへの抵抗感を薄めることができるかもしれません。また、今後各電子カルテベンダーの努力で、インターフェースがより使いやすい電子カルテが登場することで運用に対する抵抗感も下がってくることでしょう。
◆ セキュリティリスクが高まる場合がある。
各ベンダーの電子カルテではデータの暗号化やアクセス制御を標準機能として実装されていることも多いですが、医療機関ごとのIT環境次第では不正アクセスによる情報漏洩などのリスクがあります。各医療機関では厚生労働省の策定する「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の最新版を常に確認し、ガイドラインに則った環境を整える必要があるでしょう。また、停電や災害時に電子カルテが使えるよう復旧システムを各医療機関で整備しておく必要があります。
※4出典:わが国の電子カルテシステムの導入状況に関する調査結果の分析(医療情報学 28(4):225-233)
(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jami/28/4/28_225/_pdf/-char/en)
2-6.「標準化」のゴールと現在地点
日本政府は2026年までに電子カルテの普及率80%、2030年には100%を達成し日本全国での医療情報の共有体制が完成させることを目指しています。
その一環として全国の医療機関への標準化電子カルテ(または標準型電子カルテ)の普及を目指した取り組みが進められています。
2024年からは一部の医療機関で、標準化された電子カルテを活用した情報共有システムの運用が始まっています。情報共有を可能にするための電子カルテシステムの導入や既存システムの改修が進行中ではありますが、まだ紙カルテ運用が残る医療機関も多く、解決しなくてはいけない課題が残っているのが現状と言えるでしょう。
3.「標準型電子カルテ」とは?
3-1.「標準型電子カルテ」の定義
標準型電子カルテとは、電子カルテ情報の共有を実現させるための一つの施策として、政府が定めた「電子カルテの標準化」の基準に基づいて政府が開発を推進している電子カルテシステムです。無床診療所や中小病院などの小規模の医療機関ではコストや運用の面で電子カルテの導入に抵抗があり、2024年時点で49%とまだ電子カルテが普及していないのが実情です。各電子カルテベンダーでは自社製品の「電子カルテの標準化」対応が進められますが、比較的安価なコストで導入のできる電子カルテを政府主導で提供することで、電子カルテに抵抗のある医療機関を含めて情報共有基盤を活用できるようにしようというわけです。
3-2.「標準型電子カルテ」の対象医療機関
標準型電子カルテは「200床未満の中小病院」や「有床診療所」「無床診療所」が対象となる予定です。
3-3.「標準型電子カルテ」に求められる機能・仕様
厚生労働省によると、標準型電子カルテは、医療機関間での情報共有を円滑にするために開発された、クラウドベースのシステムとなる予定です。診療録の必須項目を記載できるカルテの様式は備えていますが、オーダリングシステムとの連携など、必要最低限な機能を備えたものになると言われており、民間企業が提供する多機能な電子カルテと比較すると、情報共有に特化している点が特徴です。
3-4「標準型電子カルテ」の導入コスト
2024年11月現在導入にかかるコストは未定となっています。
「標準型電子カルテ」の開発状況
2024年現在では、無床診療所を対象とした標準型電子カルテのα版(テスト版)の開発が進められており、2025年度以降にはテスト運用開始が予定されています。広範囲な導入は2026年度になる見通しです。
3-5.電子カルテ導入は「標準型電子カルテ」の発売まで待つべきか
標準型電子カルテの対象となっている「200床未満の中小病院」「有床診療所」「無床診療所」では、電子カルテの導入は標準型電子カルテの発売を待つべきか、という悩みもあるかと思います。検討の材料として以下の項目を考慮してみるとよいのではないでしょうか。
既存の電子カルテを検討した方が良いケース
- ◆早期の導入が必要な場合
現在の業務状況に明確な課題があるケースや開業の時期が決まっている場合、既存の電子カルテを導入することで迅速に業務の改善、運用が開始できます。補助金制度を使うことで導入コストを抑えることも可能です。
- ◆自院の運用、課題に合った電子カルテを選びたい場合
既存の電子カルテはそれぞれに特徴があり、診療科や運用内容などの点で自院に合った製品を選ぶことができます。
- ◆既存の電子カルテを選ぶ際の注意点
将来的に電子カルテの標準化企画に対応する製品かどうか導入までに必ず確認しましょう。
標準型電子カルテを検討しても良いが向いているケース
- ◆電子カルテ導入がまだまだ先でも良いという場合
標準型電子カルテはまだ無床診療所向けのα版のみがテストされているのみで、正式なリリースの時期は確定していません。電子カルテの導入は数年先で良いという場合標準型電子カルテの選択も視野に入れてよいでしょう。
- ◆とにかくコストが安いことを重視したい場合
標準型電子カルテは低コストで利用できることが見込まれています。
- ◆標準型電子カルテを選ぶ際の注意点
・電子カルテに関わらず、リリース直後のシステムには不具合がつきものです。不具合が運用に与える影響なども考慮が必要です。
・政府推進で開発する初めての電子カルテです。長い年月と利用者の声を受けて成熟している既存の電子カルテとは機能や使い勝手のギャップを考慮する必要があります。
・安価で導入できることが見込まれますが、コストは現在のところ未発表です。
4.まとめ
標準型電子カルテの導入は、日本の医療システムを大きく変える可能性を秘めています。患者の医療情報の共有がスムーズになり、患者中心の医療の実現が期待されます。また、医療の質の向上、医療費の削減、災害時の医療体制の強化にも貢献することが期待されています。
現在紙カルテをお使いの場合や、今後クリニックの開業をご検討の場合、政府が準備を進めている情報共有基盤を活用することが患者の満足度や院内の業務効率に大きな影響を与えるため、電子カルテ導入の検討をお勧めいたします。EMシステムズではクラウド電子カルテMAPs for CLINIC(マップスフォークリニック)をお勧めいたします。豊富なカスタマイズ機能で4倍速の入力を実現し、オフラインでも診療が可能な特殊機構を採用しクリニックのインフラとして頼れる電子カルテです。標準化の課題である運用についても一から丁寧にご説明させていただきます。またセキュリティリスク対策も万全で安心してお使いいただけます。詳しくはこちらよりお気軽にお問合せくださいませ。
この記事を書いたライター

氏名 株式会社EMシステムズ
1980年創業の医療(クリニック・保険薬局)、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を行う企業です。現在は北海道から沖縄まで、多くの全国の医療・介護施設様に当社の各種システムをご利用いただいております。
ピックアップ記事

電子カルテの種類(クラウド型・オンプレミス型)と選び方のポイント

電子カルテメーカーを比較検討する際に重視したい選定要件

電子カルテの導入費用は?費用相場やコストを抑える方法について