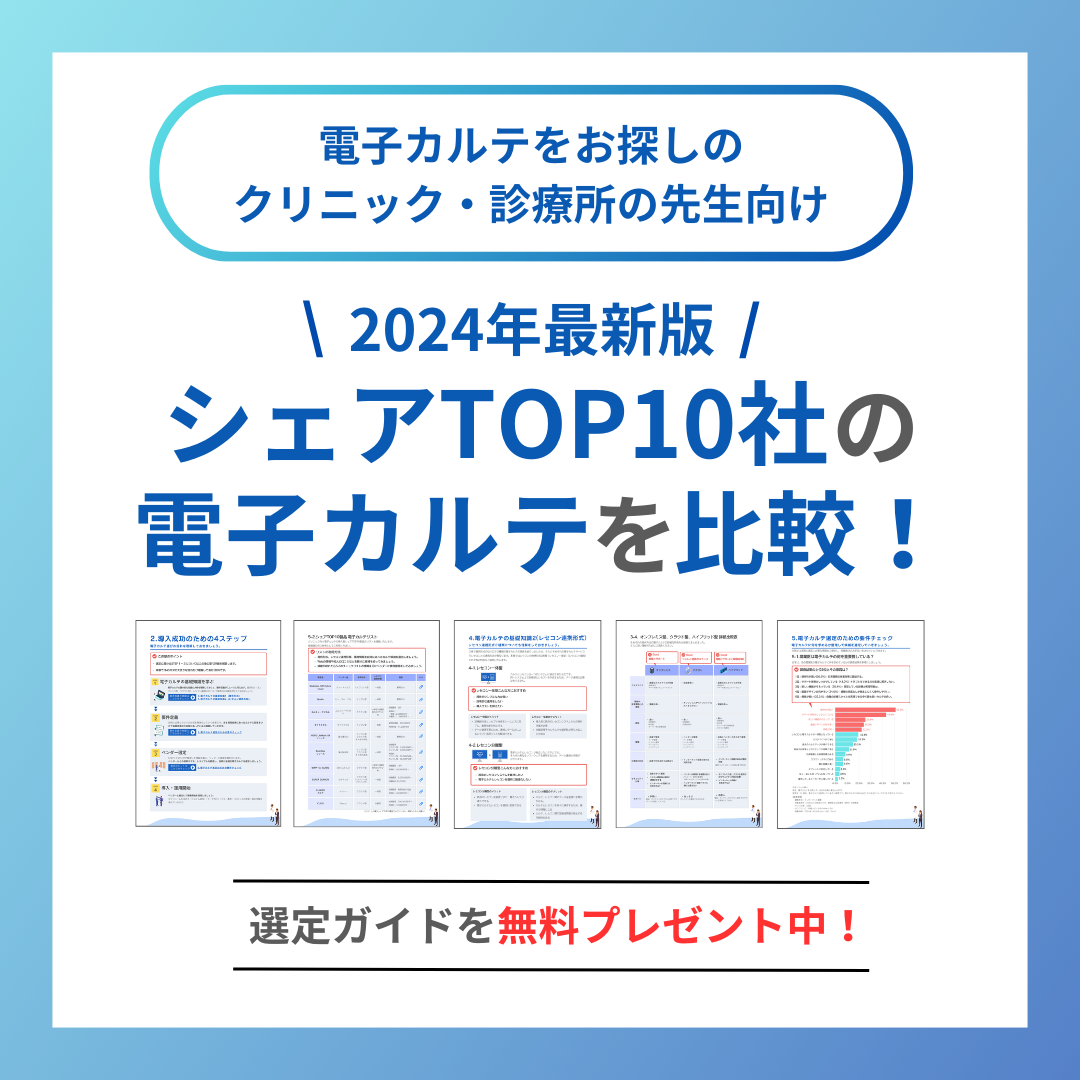経営
厚生労働省
特定疾患療養管理料とは?対象疾患や算定要件、導入のメリットをわかりやすく解説
2025.01.16
特定疾患療養管理料は、慢性疾患患者の健康管理を支援するために設けられた診療報酬制度です。患者一人ひとりに合わせた治療計画を基に継続的なケアを行うことで、生活の質(QOL)向上や疾患の重篤化防止を目指します。医療現場においては、患者との信頼関係構築や診療効率向上にも寄与する重要な仕組みです。

特定疾患療養管理料の概要
制度の背景と目的
特定疾患療養管理料は、慢性疾患を持つ患者の状態を定期的に管理し、医療の質を向上させるために設けられた診療報酬制度になります。この制度は、患者の健康状態を長期的に維持し、疾患の重篤化を防ぐことを目的としています。また、医師と患者との関係を深め、より良い医療提供のための基盤を整える重要な役割を果たしています
患者一人ひとりに合わせた治療計画や生活指導を行うことで、患者の生活の質(QOL)を向上させることが期待され、特に慢性疾患の対応においては、継続的なフォローアップが必要とされます。
さらに、慢性疾患が増加する社会的背景の中で、この制度は医療費の適正化や患者満足度向上にも寄与しています。
特定疾患療養管理料の対象となる患者と疾患
主な対象疾患
以下の慢性疾患が、特定疾患療養管理料の対象として挙げられます。
・結核
・悪性新生物
・甲状腺障害
・処置後甲状腺機能低下症
・スフィンゴリピド代謝障害およびその他の脂質蓄積障害
・ムコ脂質症
・リポ蛋白代謝障害およびその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る。)
・リポジストロフィー
・ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
・虚血性心疾患
・不整脈
・心不全
・脳血管疾患
・一過性脳虚血発作および関連症候群
・単純性慢性気管支炎および粘液膿性慢性気管支炎
・詳細不明の慢性気管支炎
・その他慢性閉塞性肺疾患
・肺気腫
・喘息
・喘息発作重責状態
・気管支拡張症
・胃潰瘍
・十二指腸潰瘍
・胃炎および十二指腸炎
・肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
・慢性ウイルス肝炎
・アルコール性慢性膵炎
・その他慢性膵炎
・思春期早発症
・性染色体異常
・アナフィラキシー
・ギランバレー・症候群
これらの疾患を抱える患者に対して、適切な診断と管理を行うことで、病状の進行を抑え、患者の生活全般における安定を目指します。また、対象疾患が幅広いため、地域医療における医療機関の役割が重要となります。
特定疾患療養管理料の算定要件の注意点

対象疾患が主病であること
特定疾患療養管理料を適切に算定するためには、いくつかの重要な注意点を押さえる必要があります。まず、対象疾患が主病であることが前提条件です。これは、診療を行う患者の主たる疾患が糖尿病や高血圧症など、特定疾患療養管理料の対象として指定されているものである必要があるということです。対象疾患以外が主病の場合、算定要件を満たさないため、注意が必要です。
治療計画に基づく療養上の管理が行われていること
次に、治療計画に基づく療養上の管理が行われていることが求められます。これには、服薬指導、運動指導、栄養指導など、患者の生活改善を目指した具体的な管理が含まれます。これらの管理が行われ、計画的に患者の健康状態がフォローアップされていることを診療記録に明確に残すことが重要です。
算定頻度は月2回まで
さらに、算定頻度は月2回までというルールがあります。このため、毎回の診療内容が適切に記録され、算定が正当化されるよう注意を払う必要があります。また、過剰な算定や記録不足は不適切な請求と見なされる可能性があるため、診療内容を正確に把握し、適切な記録を残すことが求められます。
これらの要件を正確に理解し、遵守することで、特定疾患療養管理料を適切に算定しつつ、患者への良質なケアを提供できます。上記以外の要件や変更などは厚生労働省の通知を確認するようにしましょう。
出典:厚生労働省「医科診療報酬点数表に関する事項」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293312.pdf
算定が認められないケース
算定が認められない場合として、以下が挙げられます:
- 管理計画書の作成が不十分
- 診療記録が不完全
- 対象疾患外での算定試み
- 法規制に抵触する診療形態での実施
これらを防ぐためには、医療機関内での適切な教育と管理体制が必要です。
特定疾患療養管理料導入のメリット

医療機関側のメリット
診療報酬収入の増加
特定疾患療養管理料を適切に活用することで、医療機関の収益が安定し、経営基盤の強化につながります。また、患者数が増加する中で、継続的な診療を可能にする収益モデルを構築できます。
継続的な患者管理による診療効率の向上
患者ごとに計画的な診療を行うことで、診療効率が向上します。例えば、診療記録が整備されることで、診察時間の短縮やスムーズな患者対応が可能となります。これにより、医療従事者の負担も軽減されます。
患者側のメリット
健康状態の継続的なフォローアップ
定期的な診察と指導を受けることで、患者は自分の健康状態を正確に把握することができます。患者が治療に対する理解を深めることで、医療従事者との信頼関係の構築にも繋がります。
生活習慣改善の指導による疾病予防
管理計画書に基づいた具体的な生活指導が行われるため、患者は生活習慣を見直し、疾病の予防に努めることができます。また、患者自身が積極的に健康管理に関与する意識を高める効果も期待できます。
特定疾患療養管理料の運用ポイント
診療現場での具体的な活用方法
管理計画書の作成と患者との共有
管理計画書を患者と共有することで、治療方針や目標を患者側に明確に伝えることができます。また、患者の意見や希望を取り入れた計画書を作成することで、患者の協力を得やすくなります。これにより、治療の効果がさらに向上します。
チーム医療によるケアの充実
医師だけでなく、看護師、薬剤師、栄養士などの多職種が連携することで、患者ケアの質を向上させることができます。チーム医療は、特に複雑な慢性疾患を抱える患者に対して有効です。多職種の連携が、患者の満足度を高める要素となります。
患者とのコミュニケーションの工夫
定期的なフォローアップと指導内容の説明
患者とのコミュニケーションを密にし、診療の進捗や指導内容を丁寧に説明することで、患者満足度を高めることが可能です。また、定期的なフォローアップにより、患者が治療計画を遵守しやすくなります。
レセプト請求時の注意点
記録不足による算定ミスの防止
診療内容や指導内容を詳細に記録し、不足がないようにすることが重要です。記録の不備は算定ミスや診療報酬の未払いにつながる可能性があります。
最新の診療報酬改定を反映した対応
診療報酬の改定内容を常に確認し、運用に反映することで、適切な診療報酬請求が可能となります。これにより、収益の安定化が図れます。
まとめ
特定疾患療養管理料は、慢性疾患患者の健康管理と医療機関の収益向上に寄与する重要な制度です。患者一人ひとりに合わせた診療計画を立て、継続的にフォローアップを行うことで、患者の生活の質を向上させることができます。また、医療機関にとっても、診療効率の向上や収益安定の面で大きなメリットがあります。
特定疾患療養管理料の運用を成功させるためには、正確な記録と計画的な診療が不可欠です。患者ケアと医療経営の両立を目指し、制度を最大限に活用しましょう。
診療内容の記録にはクラウド電子カルテ「MAPs for CLINIC」の活用がおすすめです。このシステムは、オンライン診療を含む診療業務全般を一元管理できるだけでなく、患者満足度の向上や業務負担の軽減に大きく貢献します。診療予約、電子カルテ、決済機能が連携したスムーズな運用を実現し、初めてオンライン診療を導入するクリニックにも最適です。詳細は公式サイトをご覧ください。
この記事を書いたライター

氏名 株式会社EMシステムズ
1980年創業の医療(クリニック・保険薬局)、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を行う企業です。現在は北海道から沖縄まで、多くの全国の医療・介護施設様に当社の各種システムをご利用いただいております。
ピックアップ記事

電子カルテの種類(クラウド型・オンプレミス型)と選び方のポイント

電子カルテメーカーを比較検討する際に重視したい選定要件

電子カルテの導入費用は?費用相場やコストを抑える方法について